相続した土地に家を建てるには? ~手続き・費用・税金まで徹底解説【2025年最新版】~

親や祖父母から土地を相続し、「せっかくならマイホームを建てたい」と考える方は少なくありません。
しかし、相続した土地に家を建てる場合には、通常の土地購入と異なり、登記や相続税の問題、用途制限や建築基準法上の規制など、特有の注意点が数多くあります。
今回は、2025年現在の制度を踏まえて、相続した土地に家を建てる際の流れや費用、税制優遇について解説します。
最初にやるべき「相続登記」
土地を相続したら、まず必要なのが「相続登記」です。
2024年4月から不動産の相続登記は義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記をしなければなりません(正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が発生することも)。
不動産の登記をしないまま建築確認申請や住宅ローンを申し込むことはできません。
相続登記の流れは以下の通りです。
- 相続人を確定する(戸籍の収集など)
- 遺言書または遺産分割協議で所有者を決定
- 必要書類(戸籍、印鑑証明、協議書など)を準備
- 管轄の法務局で登記申請
登記自体は自分で手続きすることもできますが、司法書士に依頼するのが一般的で、費用は10〜20万円程度が目安です。
家が建てられる土地かを確認する

土地を相続しても、すぐに家を建てられるとは限りません。
「都市計画法」や「建築基準法」に定められた基準を満たしていない土地には、家を建てることができないからです。
家を建てることができない土地にはいくつか種類がありますが、特に注意が必要なのは以下のような点です。
- 用途地域:住居系地域でなければ住宅が建てられない場合があります。
- 接道義務:建築基準法では、幅員4m以上の道路に2m以上接していない土地には原則として建築不可。旗竿地や袋地は要注意。
- 市街化調整区域:農地や山林など、家が建てられないケースが多い。許可を得ても厳しい条件がつくことがあります。
相続土地の多くは郊外や農村部に位置することもあり、まずは自治体の建築指導課や農業委員会に確認が必要になります。
相続税・固定資産税・住宅ローン控除など税金面の影響は?
相続した土地に家を建てる場合の、税制上のメリット・デメリットも押さえておきましょう。
相続税の優遇「小規模宅地等の特例」
土地は「相続財産」として評価されます。
宅地の評価は「路線価方式」「倍率方式」で算出されますが、小規模宅地等の特例を使えば評価額を最大80%減額できる場合があります。
たとえば、被相続人と同居していた土地や、相続後に自分が居住する土地が対象です。
面積や土地の用途に応じて、どれだけの面積が相続税軽減対象になるかが決まります。
住宅ローン控除
相続土地に新築した家でも、条件を満たせば住宅ローン控除が使えます。
2025年度は控除率0.7%、最大13年間の控除が受けられます。
省エネ基準を満たした住宅の方が優遇されるため、設計時から仕様確認が必要です。
建築費用と資金計画

土地取得費用がかからないのは相続の大きなメリットですが、家を建てるには相応の費用がかかります。
- 木造2階建て:約2,000万〜3,000万円
- 鉄骨造やRC造:約3,000万〜5,000万円
- 外構費や諸費用:約200万〜400万円
さらに、相続登記費用、土地の測量・地盤調査費用、解体費用(古家がある場合)も必要です。
解体費用は木造で100〜200万円、RC造では300万円以上になることもあります。
資金計画を立てる際は、相続税や不動産取得税(新築部分のみ)、登録免許税なども含めて検討しましょう。
農地・山林を相続した場合の注意点
都市部の宅地だけでなく、農地や山林を相続するケースも少なくありません。
農業をする予定がないので、その土地に家を建てたいという場合にはどうしたらいいのでしょうか?
農地として登記されている土地に家を建てるには「農地転用」の許可が必要です。
その土地を管轄している農業委員会(場合によっては都道府県知事)に申請し、農地から宅地へと土地の用途を変更しなくてはいけません。
山林の場合はさらに宅地造成が必要になることが多く、地盤改良や開発許可に大きなコストがかかります。
造成費が建築費を上回るケースもあるため、事前に専門業者に見積もりを依頼しておくことは必須です。
家を建てる以外の選択肢も
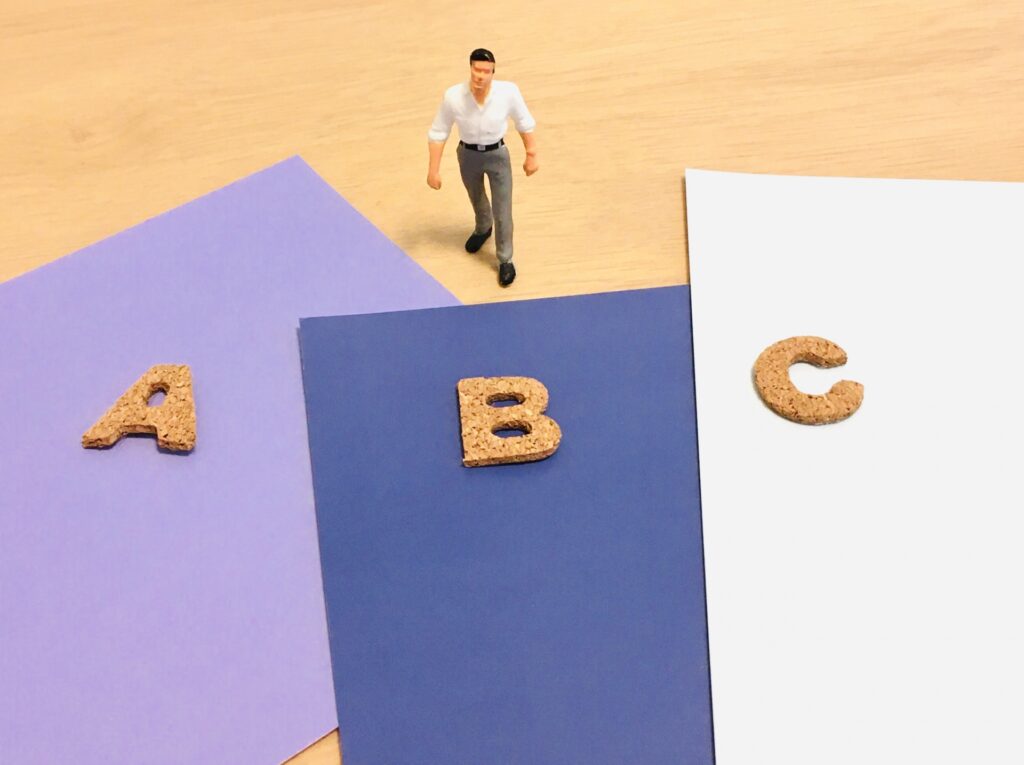
相続した土地に必ず家を建てる必要はありません。
- 売却:不要な土地は売却し、資金を住宅購入に充てる
- 賃貸活用:駐車場やアパート経営で収益化する
- 相続土地国庫帰属制度:どうしても活用できない場合、要件を満たせば国に引き渡すことも可能(2023年制度開始)
土地の条件や立地によっては、建築よりもこれらの方法が合理的な場合もあります。
まとめ
相続した土地に家を建てるには、まず相続登記を行い、土地を自分の名義にしましょう。
その上で、建築可能かどうかの法規制チェック、資金計画や税制優遇の確認を行います。
相続税や住宅ローン控除制度は複雑ですが、うまく活用すれば大きな節税効果が期待できます。
税制度については宅地を建てる前に必ず確認しておきましょう。
農地や山林などは建築のハードルが高いため、慎重な検討が必要です。
相続した不動産の対応にお困りの方は、専門家集団である荒井会計事務所まで、ぜひ一度ご相談ください。