不動産で赤字が出たら「損益通算」で節税しよう!
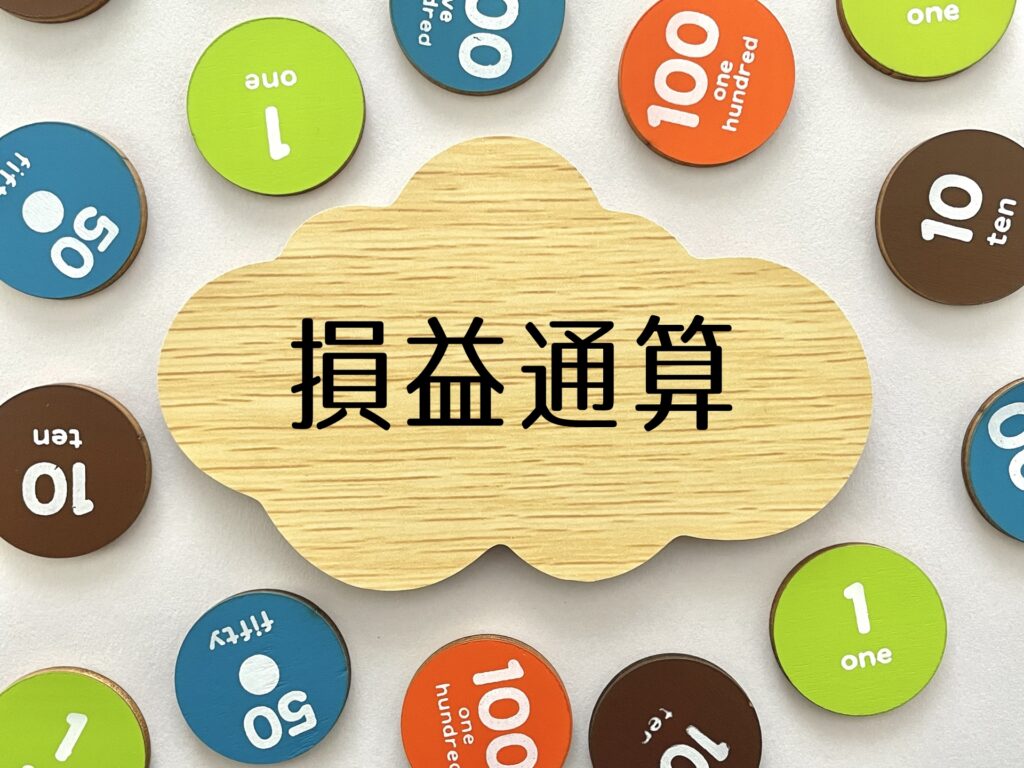
不動産オーナーの方であれば、そろそろ確定申告の準備をする時期ですね。
2024年度の所得の申告時期は、
2025年2月17日〜2025年3月17日となっています。
さて、不動産を売却したり、賃貸用物件を運用する中で、人によっては「不動産所得よりも経費の方が高かった=赤字が出た」という人もいるでしょう。そのような方は、他の黒字所得からその赤字分を差し引いて、所得の総額を低くすることができ、これを「損益通算」といいます。
損益通算をすることで税負担を軽減することができるので、不動産で赤字が出ている方は必ず行って欲しいのですが、損益通算の適用についてはさまざまな制限や注意点があります。
本記事では、損益通算の基本的な仕組みと、注意点について解説します。
「損益通算」とは?

損益通算とは、異なる所得区分の「損失」と「利益」を相殺できる制度です。
不動産投資で赤字が発生した場合、その赤字分を他の所得(給与所得や事業所得)から差し引くことで、課税所得を圧縮し、結果的に節税につなげることができます。
例えば、年間の不動産収支が50万円の赤字で、給与所得が500万円の場合、課税対象となる所得は以下のように計算されます。
500万円(給与所得) – 50万円(不動産損失) = 450万円(課税所得)
参照:国税庁「No2250 損益通算」
不動産で出た赤字を損益通算できる所得とできない所得
所得税の法律では、所得を10種類に分けて考えます。
そのうち、赤字が出た際に損益通算できるのは、「事業所得」「不動産所得」「譲渡所得」「山林所得」のみです。
この4つの所得で赤字が出た場合は、次の所得から赤字金額を差し引くことができます。
損益通算が可能な所得
- 給与所得: 一般的な会社員が、企業から得ている収入
- 事業所得: 個人事業主として得た収入
- 譲渡所得: 資産売却による利益
- 雑所得: 年金や副業収入など
損益通算ができない所得
- 株式やFXなどの先物取引に関する所得: 分離課税扱いのため相殺できない
- 退職所得: 別枠で課税されるため損益通算の対象外
不動産の損益通算で注意すべきポイント

では次に、よくありがちな損益通算の間違いについて紹介します。
ローンの元本返済分は経費にならない
不動産投資では、ローンを利用するケースが一般的です。
しかし、ローンの元本返済部分は経費として計上できません。
経費に計上できるのは支払利息部分のみです。
例:毎月の返済額が10万円で、そのうち利息が3万円の場合、経費として計上できるのは3万円のみ。
損益通算の適用外となるケース
一般的に、趣味や娯楽、保養のために所有していた不動産については、譲渡した際に損失が発生しても、損益通算をすることができません。また、不動産の貸付や、土地などを取得する際に借りたローンの利子部分は、損益通算の対象外となります。
節税には、まず青色申告の特典を活用しよう
損益通算をして節税を、と考えている人は多いと思いますが、そのためには確定申告が必要です。そして、確定申告をするのであれば、控除額最大65万円となる「青色申告」を申請しておきましょう。
青色申告を選択することで、以下の特典を利用できます。
- 最大65万円の青色申告特別控除
- 損失が生じた場合、3年間の損失繰越が可能
- 正確な記録に基づく申告で税務調査リスクを軽減
損益通算を活用した節税の具体例
では、不動産譲渡や不動産を運用するにあたって大きな損失が発生した場合、どのように損失通算をしていけば良いのか具体的に見ていきましょう。
例1:賃貸物件を所有しているAさんの場合
- 年間家賃収入: 240万円
- 経費: 280万円(減価償却費50万円、修繕費20万円、ローン利息50万円、管理費・共益費160万円)
- 不動産所得: -40万円
Aさんは給与所得500万円を得ているため、以下のように課税所得を圧縮できます。
500万円(給与所得) – 40万円(不動産赤字) = 460万円(課税所得)
他にも、所有している賃貸物件で大幅な修繕費がかかった場合も、損益通算に大きなインパクトがあります。
外壁塗装や、配管、給湯器などのリフォーム費用は数十万円単位になりますので、忘れずに差し引くようにしましょう。
例2:不動産を売却したBさんの場合
- 不動産売却価格 2,000万円
- ローン返済: 2,000万円、諸費用:200万円
- 不動産売却益 -200万円
Bさんが個人事業として事業所得1,000万円を得ているので、以下のように課税所得を圧縮できます。
1,000万円(事業所得)- 200万円(不動産赤字) = 800万円(課税所得)
損益通算を利用する際のリスクと注意点
損益通算は便利な節税手法ですが、不動産投資全体のリスクを無視してはいけません。
リスク1: 赤字が続くと資金繰りが厳しくなる
損益通算は税負担を軽減しますが、赤字が続くとキャッシュフローが悪化し、資金繰りに影響を及ぼします。
リスク2: 税務調査のリスク
不動産投資による損益通算を頻繁に利用している場合、税務署からの調査対象になる可能性があります。
帳簿や領収書を適切に保管し、申告内容を正確にすることが重要です。
まとめ

不動産の損益通算は、税負担を軽減し、資産形成を効率化するための有効な手段となります。
しかし、適用条件や制限を正しく理解し、最新の税制改正に対応することが重要です。
特に2025年から適用されるインボイス制度や青色申告の要件を見直し、適切な税務処理を行いましょう。
確定申告や、不動産の損失通算などで疑問点をお持ちの方や、事務作業に不安のある方は、専門家集団である税理士法人荒井会計事務所にぜひご相談ください。
不動産オーナーの皆さんは、確定申告が毎年のことになりますので、慌てて準備をするのではなく、予め作業の準備をしておきましょう。